前野宏のMind and Heart 第7回
「北見便り あやのひと声」

先日、道東を旅行しました。釧路に一泊したのですが、動物好きの妻が動物園に行きたいと言ったので、釧路市立動物園に行きました。動物園自体はちょっと地味な存在でした。園内を歩いていると結構大きな鳴き声を聞きました。ちょっと風変わりな鳴き声だったので、何の動物かなと思っていたら、それは丹頂鶴の声だということが分かりました。あのかよわそうな鶴の姿とは不釣り合いな大きくてあまり美しくない声でした。外敵の接近を知らせるためにあのような鳴き声になったのかも知れません。
今日はそんな「鶴のひと声」ならぬ「あやのひと声」というお話しです。
「あや」さんは過去2回連続して登場した北見赤十字病院で私と一緒に外来で働いてくれている看護師の小室綾さんのことです。
私は昨年4月から主に緩和ケア内科の外来と訪問診療を担当してきました。そして、私のアシスタントをしてくれているのが、あやさんです。あやさんは私にとって必要欠くべからざる存在です。要するに大変優秀な緩和ケアのナースなのですが、それは具体的にどういうことなのかをお話ししましょう。
先日もこんなことがありました。その患者さんは終末期ではなく、がんの治療による痛みとしびれを長く患っている女性の患者さんでした。治療の科と一緒に緩和ケア内科にも通っておられます(併診と言います)。数年の間、歴代の緩和ケア内科医師が関わっており、すでに私で4人目だったと思います。ただ、私は使われている医療用麻薬の量がちょっと多いなという印象を持ちました。長い間医療用の麻薬を使用している患者さんはともすると頓用の薬を使いすぎる傾向があるので、定期で使用している薬の量が多くなる傾向があるのです。私はもう少しお薬を減らすことができるのではないかと考え、外来のたびに少しずつ薬の量を減らすように調整していました。ただ、病状は安定していたので、そろそろ「こんなもんかな」という思いでした。ところがある日の外来で、あやさんが私の耳元で「先生、この方カロナール使われてなかったみたいです。」とささやいたのです。そう言われて、過去の処方歴を調べてみると確かに使われていなかったみたいなので、ご本人にも確認してみたら、やはりそのようでした。カロナールは頭痛や新型コロナの発熱に使ったりする極めてポピュラーな薬です。しかし、痛みにも効果があり、この薬を一緒に使うことで、頓服の医療用麻薬の使用を減らす事ができる可能性があるのです。私は目からうろこの思いでした。
これはほんの一例です。本来、あってはならないことなのですが、時間が限られている外来診療の中で時々、見落としや漏れていることがあるのです。そういったことをあやさんはぼそっと耳元でささやいてくれるのです。ある時には「先生、この方の住所は○○でしたね。」とささやいてくれます。そこは遠方で訪問診療を導入困難な場所なのです。また、ある時は、「先生、この方は独居でしたよね。」とささやいてくれます。その方は通院が困難になると入院を考えなければならなくなるのでした。このように「あやの一声」は鶴の声のように大きくはないのですが、私が見逃しているようなことをさりげなく伝えてくれるのです。言われ方によっては、医師のプライド(まあ、そのようなものがあってはいけないのですが)が傷ついてしまうのですが、彼女は言い方にまで配慮してくれているのです。
もちろん、あやさんは優秀なナースであるばかりではなく、患者さんやご家族へのケアもやさしく、きめ細かく行ってくれるので、患者さんやご家族からの信頼も抜群です。このようなスタッフと一緒に仕事をすることができる幸せを日々感じています。
前野宏のMind and Heart 第6回
「北見便り Just listening」

前回は、ある日の北見赤十字病院緩和ケア内科外来で出会った若い女性患者さんについてお話ししました。実はその日の午後、今度は同じくらいの年齢の男性患者さんが新患で受診されました。今回はその方のことをお話ししましょう。
彼は奥様の付き添いで車椅子に乗って診察室に入ってこられました。車椅子に乗っていましたが、かなりがっちりとした大柄な方であることは見て取れました。彼は少しうつむき加減でつばのついた帽をかぶっているので、目線が合いません。診察室がいきなり重い雰囲気に変わりました。
彼は消化器がんで3年前に手術を受けたのですが再発し、抗がん剤を受けていました。そして再発部の痛みのコントロールのために私達の外来を紹介され、受診されたのです。こういう状態で緩和ケアの外来を受診される方は「とうとう緩和ケアに来ることになってしまったか。」という思いで来られるのが普通だと思います。彼の雰囲気からそのことが感じられました。彼はあまり目線を合わせてはくれませんでしたが、会話はしっかりとされました。彼の問題点は、薬を飲むことに強い抵抗感があることでした。話をじっくり聴いてゆくと、どうやら消化器内科で処方された鎮痛薬も指示通りには飲んでおられないことが分かりました。それではお薬の効果は十分に出てこないだろうなと思いました。
さらにいろいろとお話を聞いてゆくうちにある事実が分かったのです。彼は小学生の時に病気で入院した病院で、にがい漢方薬を看護師さんに無理矢理飲まされたのだそうです。それ以来、薬に対する強い抵抗感(恐怖心?)が出来上がってしまったようです。そういったお話しを聞かせて頂くまでに小一時間かかったでしょうか。そして飲み薬ではなくても、貼り薬や口の中で吸収される舌下錠といった選択肢あることを一つ一つ説明し、彼と話し合いながら、最終的にはなんとか処方を終了しました。そして、診察が終わろうとしていた時気付いたのは、診察室に入ってくる時に下を向いて目線を合わせようとしなかったこの男性がその時には私の顔をはっきりと見て、ニコッと微笑んで下さったのです。それは感動的なひとときでした。診察終了後、いつも同席してくれている小室看護師(前回も登場しました!)と「彼、最後に笑ってくれましたね。」と同じ感想を共有したのでした。
ただ単に一生懸命にお話を聞くということがいかに大切か、改めて認識させられました。急性期医療の現場ではなかなかそれは出来ないことだと思います。であればこそ、私達緩和ケアの存在意義があるということも感じさせて頂いた患者さんでした。
こういう方々との出会いによって、私達はまた勇気づけられるのです。
前野宏のMind and Heart 第5回
「北見便り 研修医の温かい手」
私は2年前から毎週2日間、北見赤十字病院で緩和ケア内科医として仕事をしています。時々北見のお話をしたいと思います。
私は主に外来患者さんを担当しているのですが、今回はある日の外来で出会ったとても印象的だった二人の若い患者さんについて2回に分けてお話ししたいと思います。若いと言ってもお二人とも40代半ばの方です。でも、私達が緩和ケアで出会う患者さんの大部分は70代以上の高齢者ですので、40才代の方はとても若い方なのです。
その日の午前中の外来に見えたのは女性の患者さんです。その方は車椅子に乗って診察室にお母様と一緒に入ってきました。彼女はかぶっていた毛糸の帽子をいきなり取って、あいさつをされました。彼女の髪の毛はほとんどが抗がん剤によって失われていました。彼女の行動はあいさつのために帽子を取ったというより、「自分はこういう者です。」ということを暗に伝えようとされたのかも知れません。そして帽子を取ると同時に彼女は涙されたのです。彼女の心の痛みが伝わってきました。それを見たお母様も泣き出し、診察室は収拾がつかない状態になってしまいました。私はどうしたものかと思いましたが、「おつらいんですね。」と声をかけました。すると「いいえ、ホッとしたんです。」と、ちょっと意外な言葉が返ってきました。彼女は2年前に乳がんの手術を受けたのですが、とても悪性度の高いがんであったらしく、抗がん剤、手術を繰り返しましたが、急速にがんが体中に広がり、痛みの緩和のために緩和ケア内科外来を紹介されたのでした。彼女の涙は2年間の病気との闘いがいかに過酷であったか、そして恐らく受診したくはなかった緩和ケアにとうとう来てしまったという思いが入り混じったものであったと想像されました。現在、外科医が主治医となって化学療法を行っているのですが,主治医からの紹介状では、「今の治療が効果が無ければ、もう積極的な治療は困難」という情報が書いてありましたし、そのことは彼女も分かっているようで、「今度の治療の効果が無ければ、治療は止めるつもりです。」と。「不安や落ち込みはないです。説明はすべて聞きたいです。」と気丈に言われました。
いろいろお話をしているうちに気持ちも落ち着いたのか、もう、彼女の目に涙はありませんでした。「つらさがやわらげば、出来ることはやっていきたいです。」と彼女の気持ちはすでに前を向いていました。その言葉に彼女の覚悟を感じました。
この受診にはもうひとつ小さな感動的なシーンがありました。診察の時、2年目の女性研修医が電子カルテの記載のために患者さんの傍らに座っていました。患者さんが涙された時、すっと手が伸びて患者さんの背中をさすっていたのでした。あまりのさりげなさにすぐには気づかなかったくらいです。患者さんの苦しみに寄りそうこころ、つまりホスピスのこころをこの若い研修医はすでに身につけていたのでした。患者さんの診療の後、同席していた看護師のKさんとその研修医の行動について、「すごいねー」と語り合ったのでした。
前野宏のMind and Heart 第4回
「村上明子さんのインタビュー-その3-『そしてザンビアへ』」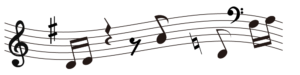
村上明子さんが今年の6月でピアノタイムを終了したのは彼女が今年の秋頃、海外青年協力隊(JAICA)としてアフリカのザンビアに派遣されることが決まっているからです。私(前野)はそのお話を聞いてとても驚きました。あまりにも突然なことでしたし、村上さんとザンビアがあまりにもかけ離れていたからです。恐らく、彼女からこのお話を聞いた方は皆さん同じように感じたことと思います。今回は彼女のザンビア行きについて伺いました。私はこのお話が「ホスピスのこころ」に通じると思い、とても興味深く伺いました。
前野:それではザンビア行きについて伺いたいと思います。今、村上さんはどういう気持ちでザンビアに行こうとされているのでしょうか。
村上:毎日その時々で沸いてくる気持ちが変わります。たくさんの期待と少しの不安です。やってみたいこと、チャレンジしてみたいことがある一方で、語学や慣習の違いの心配から、自分が思っていることができるのか、そもそも相手から求められていなくて、冷たい対応などをされたらどうしようかなど考えています。
前野:どうしてザンビアなのですか?
村上:昔から途上国に関心があったのですが、高校生の時に南アフリカのアパルトヘイトを題材にした活動をすることがあり、それがきっかけで特にアフリカに興味を持つようになりました。音楽の位置づけは人によって様々で、その音楽が途上国にどのように役立つのか、助けになるのかがしばらく見えてこなかったのですが、いろいろな活動の中でも、特にアンサンブルグループ奏楽で幅広い活動の場を与えていただいたことで、音楽でも何かできることがあるかもしれないと思いました。音楽をコミュニケーションツールのひとつとして人と関わることができれば、そこからその人にとって必要なことが何かわかるのではないかと思ったのです。きっかけはいくつもあるのですが、コロナを経験したり、ウクライナ侵攻があったことで思うこともありましたし、応募に年齢制限もあったので、タイミングとしては今かなとエントリーすることにしました。私は海外で生活したこともないですし、アフリカに行ったこともありません。なので体制が整っているJICAを通して行くのが良いかなと思いました。
前野:ザンビアというのはJICAの方と相談した中で出てきたのですか?
村上:アフリカ、音楽、資格条件、語学レベルで当てはまったのがザンビアでした。
前野:やはり、あちらでもピアノはされるのですね。
村上:したいですね。ピアノタイムをやってきて、皆さんの反応などを見てきているので、活動外にそういったこともチャレンジしてみたいと思います。
前野:具体的にはどのような活動をなさるのですか。
村上:あちらの大学に配属されて、そこの学生さんにピアノを教えたり、その向上のためのワークショップや勉強会、コンサートなどの活動があります。後は自分の仕事が終わって自由な時間があれば、その時間でやりたいと思っている活動ができればと思っています。子供達と関わることができればやってみたいですし、病院や施設にも行ってみたいです。これまでしていた音楽をそういう所に持って行ったらどうなるのかなということが気になります。
前野:そうすると、当院でのピアノタイムの経験が生かされそうですね。
村上:そうですね。こんなにも受け入れられるんだなと正直驚きました。みんながみんな音楽を好きなわけではないでしょうし、本当に具合の悪い時には放っておいてほしいという方もいると思いますが、音楽によってこんなに元気になったり喜んでくれる人がいるんだということを経験し、とても嬉しかったですし、音楽の力を感じました。そしてそれはやはり生(演奏)の力なのだとも思いました。
前野:職員とも話しているのですが、2年間経って必ず帰ってきて頂いて、帰朝報告会をして頂きたいです。村上さんがどのようなことを経験してきて、学んでこられたかを教えてほしいですね。
村上:そのようなお話しができるくらい頑張りたいです。そうですね。そういった緊張感もありますね。旅行に行くのと違って、この派遣には責任を感じてます。
前野:職員と話していても、皆「すごいよね。」と言っています。そもそも、ザンビア知らないです。(笑い)私もそうですが、日本人にとってアフリカってかなり遠いです。映画か何かの世界ですね。あるスタッフは「アフリカというと怖い」と言っていました。村上さんがそのようなところに行くのは偉いねという気持ちだと思います。分からない世界に行くというのはチャレンジですよね。
村上:ちょっと分からないくらいだから行けるのかなと思います。ふと我に返ると怖くなって、考えすぎたら躊躇してしまうから、ちょっと分からないくらいが良い思っています。
前野:最後になりますが、村上さんにとって「ホスピスのこころ」とはどういうことでしょうか。
村上:人間力ではないでしょうか。自分そのものを差し出すという。
前野:私は村上さんが今回、ザンビアに行かれることは「ホスピスのこころ」そのものだと思っています。「ホスピスのこころ」は弱い方の目線に立つことです。それは、その人の考え方に沿うとかその人に受け入れられる行動をするという積極的な行動だと思います。ザンビアのことに興味を持って支援する方法はいろいろあると思います。寄附をするとか。でも、村上さんがわざわざ現地に行って、活動するということはまさに自分を提供することですね。
村上:そうですね。募金をするくらいなら貯めてでも良いから自分が行きたいと思っていました。自分を提供したい。自分が試されていると思います。自分がどういう者であるかあからさまになると思います。
前野:ザンビアに2年間行かれた明子さんはきっと成長して帰ってこられることと思います。みんなそのことを楽しみにして待っています。少し寂しいですが、2年後にはまたお会いできることを楽しみに、送り出したいと思います。どうかお元気で。心からご活躍をお祈りしております。
前野宏のMind and Heart 第3回
「村上明子さんのインタビュー-その2-『明子さんのピアノタイム』」
当グループは2年前に札幌市清田区平岡の地に新築移転致しました。その際、3階ある病院の各フロアと地域緩和ケアセンター(ルイカ)に合計4台のピアノを設置しました。その年の9月からそれらのピアノを使って、毎週「明子さんのピアノタイム」で村上さんが患者さんを前に演奏して頂きました。今回はピアノタイムについてお話しして頂きました。
前野:当グループの理念である「ホスピスのこころ」を表す「三つのH」とはHospitality(おもてなし),Healing(癒し),Hope(希望)です。私は音楽はその全部に関わってくる大切な要素だと考えています。アンサンブルグループ奏楽の代表である岩崎さんのご尽力によって、各階にピアノを設置することが出来ました。患者さんにとっては階を移動しないでピアノの元で生の音楽を聴くことができるのはとてもありがたいことだと思うのですが、ピアニストにとっては同じ曲を何回も演奏しなければという事で、大きな負担がかかると思います。村上さんと事前に話し合った時にそれをやって頂くことになって、ルイカも入れると4回演奏して頂くことになります。最初からそのスタイルは何も変わっていませんね。
村上:ただ単に同じ曲を30分、4回弾くというのはすごく大変ですが、ピアノがそれぞれの階で違い、聴いてくださる方も違うので、同じ曲を弾いても毎回違う気持ちになりました。それぞれ、楽しさがあります。
前野:大変じゃなかったですか。
村上:大変は大変ですけれど、それより、今日はこの階にどんな方がいらっしゃっているのかなとか、皆さんの様子はどうかなといったことを考えながら、じゃあどうやって弾こうかなとか、同じ曲でもちょっとテンポを変えたり、音量を変えたり、そういう工夫が出来る楽しみがありました。
前野:毎週、曲を選んだり、準備をされたりというのは結構大変な労力だったんだろうなと思うんですが。
村上:楽ではなかったですね。(笑い)苦労したのは二つあって、一つはプログラムを考えること。弾きたい曲がある時はスムーズに出て来るのですが、だんだんアイディアが尽きてくる。季節や行事、その時話題になっているもの、自分の気分など、きっかけがないと閃きにくくなります。1個閃いて3曲くらい決まっても、その後どのようにしようかといったプログラムの構成を決める大変さと、もう一つは練習時間の確保がやはり大変でした。
前野:連載小説を書いていて、締め切りに追われる作家の気分ですね。
村上:慣れている曲は楽しめるけれど、初めての曲はとても緊張しますし、でも、苦しみもまた楽しいというか、自分の経験にも勉強にもなって、結局は良いことばかりなのですが。
前野:コロナで何回かお休みしたけれど、村上さんの都合で休んで事はなかったんじゃないですか?
村上:1回だけあります。ずいぶん前から決まっていたお仕事があり、始まったばかりの時に1度だけ。
前野:約2年間になりますが、すごいことですね。
村上:どうしてそれが出来たのかなと考えると、患者さんがいつ亡くなるか分からないという、今を生きるということを教えて下さったからだと思います。リクエストも今度ではなく、今できるならやろうということを教えてくれたのはピアノタイムです。
前野:リクエストは結構ありましたか。
村上:ありましたね。たくさんありました。振り返ると、リクエストの半分は知らない曲で、弾いても弾いても初めて出会う曲の多さに圧倒されました。
前野:2年間、ピアノタイムをやってこられて、感想とか学んだことを教えてください。
村上:ありすぎますね。(笑い) 「人に寄りそって行く」ということを身をもって教えて頂きました。その人に寄りそって演奏をするというのは、言ってみれば、「チューブにでも入っていくような感じ」。私の中では、広がって行くと言うより、何か筒の中に入って行くような感じなんです。演奏しているうちにその筒の中に入っていけると一体感になれた感覚になります。自分が気持ちよく弾いている時にはもしかしたら患者さんは心地よくないのかも知れません。私が開放的になっているだけなのかも知れない。コンサートホールで弾くのとは違う感じです。それが、他では出来ない経験でした。 そして、当たり前の事なのですが、ピアノタイムを通して、よりそれが確かになったことがあります。心をきれいにしておかなければと思いました。具合の悪い方というのは何か自分にはないものが見えるんだろうなと、見透かされているような気持ちになったことがあるんです。雑念を消す、そうですね、お坊さんの「無になる」というのに近いのでしょうか、自分の事情とか感情とかを抜きにして、いかにまっさらになるかということが試されたような気がします。
前野:音楽を通して患者さんと繋がるというようなことなのでしょうか。そういったことは選曲から始まりますね。明るすぎてもいけないし、暗すぎてもいけない。それも人によって違いますしね。
村上:それもすごく感じました。本来の自分ではない事をすると見透かされる。その人にとって癒やしにならないと思います。
前野:それは普通の演奏会とは違うんですね。
村上:違いますね。空間なのか距離なのか、患者さんの置かれている状況なのか。私が気にしすぎなのかも知れませんが。 実は私は毎週ここに来ることで、自分を元に戻せるんです。いろいろなことがあっても、ここに来ると一旦リセットされるのです。
前野:最近の言葉で言うと、自分を「整える」ということでしょうか。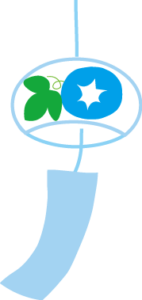
村上:本当に「整える」です。前にも話したことですが、これまでは病院に行くと疲れることがほとんどでした。でも、ここに来るとスッキリして、まるでサウナに入った後のようにスッキリとするんです。活力になります。(笑い)不思議ですよね。病院って、病人のいる所なのに。それは患者さんばかりでなく、スタッフの皆さんの出している空気もそうさせるのかもしれません。病院に行って嫌な気持ちになるのは何でだろうと思うのですが、スタッフの方やお医者さんとのコミュニケーションや関わり方が原因であるところがあると思います。私はここに来て、一度も嫌な思いをしたことがないのです。
前野:そう言って頂けるとうれしいです。普通、病院は医療者から患者さんに何かを提供するところだと思うのですが、実は患者さんから私達は影響を受けます。「ホスピスのこころ」は私達医療者が患者さんの目線でものを考えたり、行動したりするという考え方ですが、私達が患者さんからケアされたり、力を得たり、喜びを与えられたりということが沢山あるんです。それは表面的なことではなく、深い静かなことだと思います。今のお話を聴いていると、演奏している方も患者さんからのパワーを感じて、整えられるということなのかもしれませんね。
前野宏のMind and Heart 第2回
コラム Mind and Heart 第2回![]()
「村上明子さんのインタビュー -その1-『在宅ホスピスとの出会い』」
札幌在住のプロのピアニスト村上明子さんは当グループ(札幌南徳洲会病院、ホームケアクリニック札幌、緩和ケア訪問看護ステーション札幌)と大変関わりの深い方です。2021年9月から毎週行われてきた「明子さんのピアノタイム」が2023年6月に終了しました。村上さんは私達の理念である「ホスピスのこころ」に共感され、音楽を通して、当グループに大変貢献して下さいました。彼女へのインタビューを3回にわたってご紹介します。まず、第1回は彼女と私達との出会いと在宅ホスピスとの関わりについてです。
前野:2017年にアンサンブルグループ奏楽のメンバーとしてホームホスピスコンサート(プロの演奏家が在宅ホスピスを受けている患者さんのお宅に伺って演奏させて頂くミニコンサート)で、Hさん宅で演奏して頂いたのが最初でしたね。その時の思いではいかがでしょうか。
村上:施設などでの経験はありましたが、終末期の患者さんの前で演奏するのは初めての経験で、正直気持ちの置き所が分からなかったです。(写真)私はピアノの方を向いていて、患者さんの顔を見る余裕は無かったので、むしろそれは助かったと思います。その時にHさんのリクエストでショパンのノクターン(遺作)を演奏しました。
Hさん宅でのホームホスピスコンサート
(ピアノを弾いているのが村上さん)
前野:その後、私は村上さんが演奏するモーツアルトのピアノ協奏曲を聴いて、個人的にファンになってしまったのですが、そういったご縁があり、2020年2月に村上さんのお祖母様が末期がんになられ、最期まで自宅で過ごしたいということで、私達のクリニックに依頼がありました。そして私が主治医になり、自宅でお看取りさせて頂きました。1ヶ月という短い関わりでしたが、毎回訪問診療のたびに村上さんがいて下さり、お祖母様のご自宅にあるピアノで演奏もして頂きました。(それを「グリコのおまけ」と名付けさせて頂きましたね)
村上:がんで余命が1ヶ月と聞いて、悲しかったのですが、前野先生達がいつもされているお仕事を近くで見ることができるという機会を得ることができて、おばあちゃんが与えてくれた最後のご褒美だったような気がします。
前野:私も(毎回村上さんの演奏を聴かせて頂き)得をしました。(笑い)
村上:ホームホスピスコンサートの意味がここで分かりました。特別だけれど特別ではなかった。今私が病院でやっている「ピアノタイム」は特別なことではなく、日常的な事として行っています。患者さんやご家族の皆さんの空間を一緒に楽しむことが出来たのが良かったと思います。Hさんの時にはまだそういうことが分からず、特別な感じとして演奏していました。
前野:音楽の力みたいなものを感じましたか。
村上:私がピアノを弾いていると、ベッドサイドに先生がいて、おばあちゃんの呼吸が音楽に合わせて変わっていったと教えてくださいました。
前野:あの時もショパン(遺作)でしたね。あの時、お祖母様は「もうおしまいなんですね。」と言われましたね。それから眠るように意識が低下していきました。村上さんのピアノがお祖母様の魂に届いた感じがしました。そして、それから3日後にご自宅でお亡くなりになりました。その翌年、病院が新築移転された時にそのお祖母様の想い出のピアノを地域緩和ケアセンタールイカに寄贈してくださいました。本当に感謝しております。
前野宏のMind and Heart 第1回
「Mind and Heart」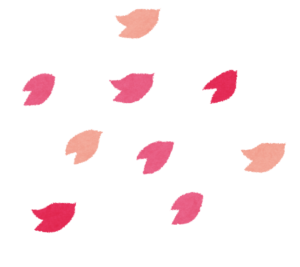
「前野宏のホスピスのこころ」は2021年1月に第25回を書いてから、筆が止まってしまいました。もしも、このコラムを楽しみにしていた方がいらしたとしたら、本当に申し訳ありませんでした。この間、いろいろなことがありました。病院では新型コロナのクラスターが発生し、外来及び新入院を受けることが出来なくなり、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけしました。一方、良かったこととしては札幌南徳洲会病院およびホームケアクリニック札幌、緩和ケア訪問看護ステーション札幌が新築移転しました。それが2021年7月で、それから早いものでそろそろ2年が経とうとしています。また個人的なことですが、私は2021年10月から毎週北見赤十字病院の緩和ケア内科をお手伝いに北見出張をするようになりました。北海道の地域の病院ではどこも医師が不足しているのです。当初は日帰りだったのですが、2022年4月からは毎週3日間、そして今年の4月からは毎週2日間北見に行っています。
このコラムでは時々、「北見便り」もお送りしたいと思います。
ということで、約2年間コラムをお休みしてしまいましたが、心機一転、再開させて頂きたいと思います。タイトルもちょっと変えてみました。「前野宏のMind and Heart」。”Mind and Heart”とは日本語に訳すと「頭とこころ」ということになるでしょうか。近代ホスピスの基礎を作ったのは、イギリス人のDame Cicely Saundersです。彼女は38才で医師になったのですが、一時、医療ソーシャルワーカーとして仕事をしていました。その時にDavid Tasmaという40才台のポーランド人の患者に出会い、恋をします。彼は胃がんの末期状態で、二人がこの世で会うことができたのは1ヶ月足らずでした。”Mind and Heart”はTasmaがCicelyに言った言葉です。彼は”I only want what is in your mind and in your heart.”(私は、ただあなたの頭とこころの中にあるものがほしい。)と言いました。そして「私はあなたの家の窓になろう。」と言って、自分の遺産として500ポンドを彼女に渡します。「あなたの家」とは自分のような末期の人が最後に過ごす場所を作って欲しい。つまり、これがホスピスのルーツになるのです。現在、Cicelyが作ったSt. Christopher’s Hospiceの窓には”Tasma’s Window”というプレートと、彼の言葉が刻まれています。ホスピス緩和ケアが急性期医療と本質的に異なるのはこの”Heart”の部分を大切にすることです。このコラムではそういったことをお伝えして行きたいと思います。
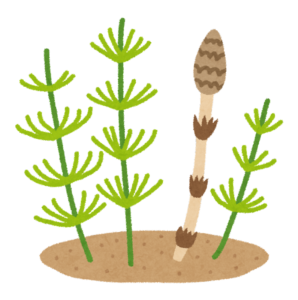 NPO法人ホスピスのこころ研究所 前野 宏
NPO法人ホスピスのこころ研究所 前野 宏
コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第25回~
『歌う回診』
2020年のクリスマスシーズンは、ホスピスの風景もいつもと違うものになりました。
私は医師になってからほぼ毎年必ずしていたことがあります。それは、病院職員による即席の聖歌隊を編成して患者さんのところを訪問し、クリスマスの賛美歌を歌うのです。「キャロリング」と呼びます。当院でも私が院長に就任した時から毎年行ってきました。当初は、事前に何日間か練習が必要でしたが、数年たった頃からはキャロリングを行う前の1時間くらい練習すれば大丈夫。レパートリーは毎年「もろびとこぞりて」「グローリア」「きよしこの夜」の3曲でずっと同じですが、混声4部合唱で、なかなかなものです。いつも医療者として働いている医師や看護師達が歌う姿に患者さんやご家族はとても感激して下さいます。
その後、私がホームケアクリニック札幌を開設してからは患者さんのご自宅を回るキャロリングも始めました。皆さん、歌のクリスマスプレゼントを大いに喜んで下さいます。
しかし、2020年はコロナ禍のため、患者さん、ご家族の前で合唱をすることは断念しました。
大変残念な事でした。しかし、実はちょっとだけ歌ったのです。
私のホスピスでの回診は毎週金曜なのですが、2020年12月25日が丁度金曜だったのです。病状が悪くなって、意識状態が下がっていたある若い女性の患者さんがいました。いつものように、回診のメンバーが車座になって、その患者さんの周りに座りました。すると、臨床心理士の阿曽先生が「クリスマスソングを歌いませんか。」とおっしゃったのです。私は「そうだ、今日はクリスマスだ」と思い出し、「きよしこの夜」を歌いました。阿曽先生も唱和して下さいました。他のメンバー達はいきなりのことで、ちょっとビックリしたようで、声が出ていたかどうかは不明です。その女性の患者さんには、きっと私たちの「きよしこの夜」が聞こえていたでしょう。この日の回診では、何人かの患者さんのところで「きよしこの夜」を歌いました。一緒に大きな声で歌って下さる方もいました。皆さん、喜んで下さいました。
回診で歌を歌う。初めての経験でしたが、歌が好きな患者さんにとっては、良いプレゼントになるなと思いました。それを機に、回診で時々歌を歌うようになりました。
80才台の女性患者さんがいました。彼女は声楽のトレーニングを受けていた方で、ホスピスのお茶会などで何度か「オーソレミヨ」を独唱されたり、指揮をされたりするような大の歌好きの方でした。ある日の回診の時に、たまたま枕元に日本の歌の歌集があったので、「何か歌いましょう。」と言って、眼に止まった「砂山」を歌ったところ、彼女は指揮をしながら、朗々と歌われたのでした。
ちょっと味を占めた私は、訪問診療で伺っているある80才台の女性患者さんが女学校時代に合唱をしていたという事を伺ったので、即席で「ふるさと」を歌ってみました。すると、この方も大きな声で歌われました。実は彼女は認知症があって、ちょっと前の会話も忘れるほどなのですが、昔覚えた歌はしっかりと歌われるのでした。感動のひとときでした。
「歌う回診」ちょっとやみつきになるかも。
ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏
コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第24回~
『こもり人と寄りそい人』
 先日、NHKテレビで「こもり人」というドラマを観ました。フィクションではありますが、多くの関係者からの取材を元にNHKの総力を挙げて作られたのと、主役の松山ケンイチとその父親役の武田鉄矢の迫真の演技も相まって、大変内容の濃い、インパクトの強いドラマでした。
先日、NHKテレビで「こもり人」というドラマを観ました。フィクションではありますが、多くの関係者からの取材を元にNHKの総力を挙げて作られたのと、主役の松山ケンイチとその父親役の武田鉄矢の迫真の演技も相まって、大変内容の濃い、インパクトの強いドラマでした。
現在、我が国における「引きこもり」の人の数は100万人以上と言われ、特に40才以上の中高年層の引きこもりの人は60万人を超えるとされています。いわゆる「8050」問題(80才の親が50才の引きこもりの子供を養っている現実)が言われていますが、最近ではそれをさらに越えて、親が死んだ後、残された子が衰弱死する「ひきこもり死」が顕在化し、大きな問題となっています。
ドラマの中で、松山ケンイチが演じる倉田雅夫(40)は家で10年以上ひきこもりの生活をしています。武田鉄矢演じる父親の倉田一夫は元教師で社会的信頼が大変厚い人でした。妻が亡くなって雅夫と二人で一軒家に生活し、雅夫の身の回りの世話はしているのですが、世間体を気にして雅夫のことは世間からひた隠しに隠していました。しかし、一夫は自分が胃がんのステージ4と分かり、自分の余命が短いことを知り、もう一度雅夫と向き合うことを決意します。
孫の未咲からいろいろと情報を得て、引きこもり経験者の集まりに出かけ、ひきこもり体験談を聞いたりすることを通して、受験や就職がなかなかうまくいかない雅夫に対し、厳しい言葉を浴びせていた自分自身が雅夫を引きこもる原因を作り出していた張本人であることを悟ります。
ある時、雅夫が自殺をほのめかすのですが、「自分は生きていてはいけないんですか」と叫ぶ雅夫に対して、一夫は「お父さんなりに、君を大切にしてきたんだ。頼む。生きていてくれればいい。それだけでいいんだ。一緒にお家に帰ろう。」と涙ながらに訴え、一夫を抱きしめようとしますが、その場で吐血して倒れてしまいます。一夫は救急車で運ばれますが、そのまま帰らぬ人となってしまいます。
ドラマの最後のシーンは一夫の葬儀のお寺の場面ですが、雅夫はメモを読みながらたどたどしい言葉ではありますが、「父は自分のために最後まで尽くしてくれました。」と会葬者にあいさつするのです。
ひきこもる人は生産性を追求する現代社会の中で、価値のない存在として考えられています。しかし、一夫が雅夫に対し、上から目線で動かそうとしてもかえって、二人の溝が深まってしまったのに対し、一夫の方から雅夫の目線まで降りて行き、寄りそおうとした時に、雅夫の気持ちは変えられました。結局、雅夫の存在を通して一夫が変えられ、一夫が変わったことにより雅夫も変えられたのです。
「ホスピスのこころは弱さに仕えるこころ」です。強い者が弱い者を上から目線で動かそうとしてもかえってお互いの距離が離れてしまいますが、強い者が弱い者に寄りそう努力をし、弱い者の気持ちを聞かせて頂くように努める時、その方の心が開かれる可能性が生まれるのです。「ホスピスのこころ」は医療の現場だけではなく、普遍的な真理なのだと思います。
ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏
コラム「前野宏のホスピスのこころ」~第23回~
『ここで私は変えられました』
ホスピスにおいて毎週金曜日に行われている総回診で、ある患者さんからありがたいお言葉を頂きました。
80才台の男性患者Aさん。回診の時には必ず奥様も一緒にいらっしゃいます。Aさんに回診で初めてお会いした時のことをはっきりと覚えています。その日も奥様がベッドサイドに座っておられました。私はあいさつをし、いつもの通りにお体のことを伺いました。そしていかにも仲睦まじそうなご夫婦の話題になりました。そうするとAさんは次のようにおっしゃったのです。「私は妻を奴隷のように扱っていました。本当に申し訳なく思っています。」真面目にそのように切り出されたAさんの言葉に私はちょっとビックリしましたが、「そのように言うことができるAさんもご立派ですね。」と言うと、Aさんは「ここ(ホスピス)の環境や、看護師さんたちの優しさがそのようにしてくれたのです。皆さんのおかげです。」と言われました。元来、Aさんはそのような優しいお人柄であったのでしょうが、仕事が忙しすぎて、やさしさを表現することができなかったのかもしれません。「元々持っていた良さが出てきて良かった。」と奥様。ホスピスの環境やスタッフのケアを褒めて頂き、私は責任者として大変うれしく、誇りを感じたのでした。
その後、毎週私はAさんの回診に伺っているのですが、そのたびにニコニコベッドサイドで微笑んでいる奥様がいます。そして、毎回、Aさんからはお褒めの言葉が出てくるのです。ある時の回診では、その数日前に高熱が出て辛かった時に、深夜帯でTさんという看護師が対応したのですが、「Tさんが、包み込むように見守ってくれた。寄りそってくれてうれしかったです。安心できたのです。」と言われました。また、受け持ちの看護師であるIさんのことを「毎朝、「おはようございます。」と笑顔で声かけしてくれるのです。親身になって寄りそってくれる。信頼感があります。」と言ってくださいました。スタッフひとりひとりのことを褒めてくださり、また私はありがたく感じました。
柏木哲夫先生は「人は生きてきたように死んでゆく」と言っています。つまり、感謝する人生を送ってきた人は感謝しながら死んでゆくし、不平不満を言う人生を送ってきた人は不平不満を言いながら死んでゆく、という意味です。私も長くこの仕事をしてきて、柏木先生のおっしゃることは正しいと思っております。しかし、まれにAさんのような方もいらっしゃいます。Aさんは80年以上の人生の最後に変わられたのです。それは、Aさんの力に他ならないのですが、そのことに私たちのチームが少しだけ関わることができたとすれば、大変光栄なことだと思います。
ホスピスのこころ研究所 理事長 前野 宏





